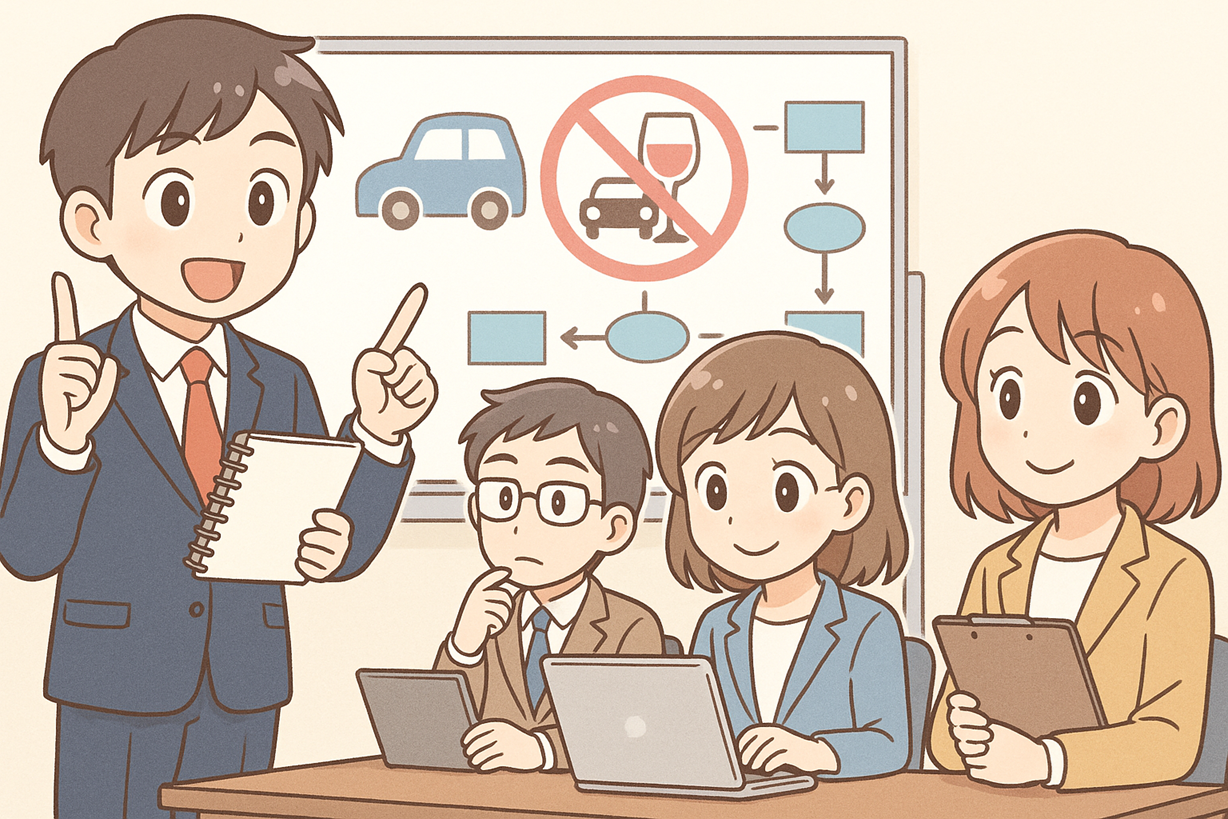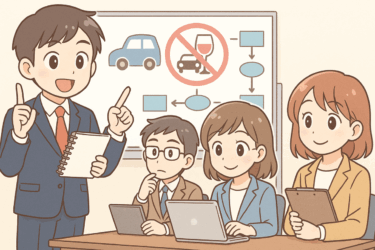どうも。
スマイルネットワークのコージリです。
企業における飲酒運転の撲滅は、単なる「社員教育」や「一度きりの研修」だけでは根付かない課題です。
なぜなら、教育は意識を一時的に変えるだけであり、時間の経過とともに記憶は薄れ、行動も元に戻ってしまうからです。
経営層や管理職が本気で取り組むべきは、「教育を仕組みに変換すること」です。
つまり、意識の変化を一過性で終わらせず、組織のシステムとして継続的に行動に落とし込むことこそが、飲酒運転ゼロを実現する唯一の道だと考えます。
そこで今回は、経営層・管理職が取り組むべき「仕組み化による飲酒運転撲滅」戦略について見解を示したいと思います。
なぜ仕組み化が必要なのか
社員が「飲酒運転をしない」と約束しても、その誓いは感情や意思力に依存しています。
しかし意思力は有限で、長時間労働やストレス、疲労によって簡単に揺らぎます。
そのため「しないと決めた」だけでは防止策として脆弱です。
ここに経営層・管理職の役割があると考えます。
仕組みを設けることで、意思力に頼らなくても安全行動をとるよう誘導できるのです。
つまり、仕組み化とは「弱さに依存しない設計」であり、個人の資質に頼らず組織全体でリスクを減らすアプローチなのです。
経営層が果たすべき役割
経営層はまず「飲酒運転ゼロ」を経営方針に明文化する必要があります。
安全は売上や利益と同等に扱うべきテーマであり、経営トップが旗を振ることで全社的な優先順位が明確になります。
さらに、方針を単なるスローガンに終わらせず、予算や人員配置に反映させることが不可欠です。
例えば、定期的なチェック体制を構築したり、アルコール検知器を全社導入したりする施策は、経営判断がなければ実現しません。
トップが姿勢を示し、組織全体に「安全は投資である」という文化を浸透させることが第一歩なのです。
管理職が担う現場実行の要
経営層の方針を現場で動かすのが管理職の役割です。
管理職が果たすべきは、日常のマネジメントに飲酒運転防止を組み込むことです。
たとえば、出退勤時にアルコールチェックを行い、そのデータを記録・共有する。
飲み会後の移動手段を事前に確認し、代行や公共交通の利用を推奨する。
こうした「確認」「記録」「報告」を日々の業務プロセスに溶け込ませれば、意識に依存しない安全文化が育ちます。
管理職が本気で取り組む姿勢を見せることは、部下にとって最大の教育でもあります。
習慣化と環境整備の重要性
仕組み化の真価は、やがて社員の習慣となる点にあります。
最初は義務感で行うチェックも、毎日のルーティンに組み込まれることで無意識の行動へと変わります。
また、環境を整えることも大切です。
例えば、社用車のカギをアルコール検知と連動させ、チェックを通過しなければエンジンがかからない仕組みを導入する。
飲み会の開催ガイドラインを整備し、幹事に移動手段確認を義務づける。
これらは社員の心理に過度な負担をかけることなく、自然に安全行動を促す環境設計といえます。
教育から仕組みへ──実践の流れ
飲酒運転撲滅のためにまず必要なのは教育です。
しかし教育は「入り口」にすぎません。
そこから行動が定着するまでをデザインするのが仕組み化です。
教育を受けた社員が実際に行動する場面を想定し、つまずきやすいポイントにサポートを置く。
たとえば、「代行手配アプリの利用方法を研修で紹介し、経費精算をスムーズにする」など、実務に直結する仕掛けを組み込む。
教育→実践→仕組み化の流れを回し続けることで、ようやく「文化」として根付いていきます。
経営層・管理職が得る未来
仕組み化された安全文化は、飲酒運転ゼロを達成するだけではありません。
社員の安心感を高め、家族からの信頼を獲得し、ひいては企業のブランド力を向上させます。
社会的責任を果たす姿勢は採用活動でも強いアピールになり、優秀な人材確保にもつながります。
経営層にとってはリスクマネジメントの観点からも価値があり、管理職にとってはチーム運営の安定につながります。
つまり、仕組み化はコストではなく未来への投資なのです。
「仕組み化」が企業を守る!
飲酒運転撲滅は教育だけでは不十分です。
経営層が旗を振り、管理職が現場で実行し、仕組みとして組織に根づかせる。
このプロセスこそが、企業と社員を守る最も確実な道です。
意思や根性に頼らない「仕組みの力」を最大限に活用し、飲酒運転ゼロを未来へとつなげましょう。