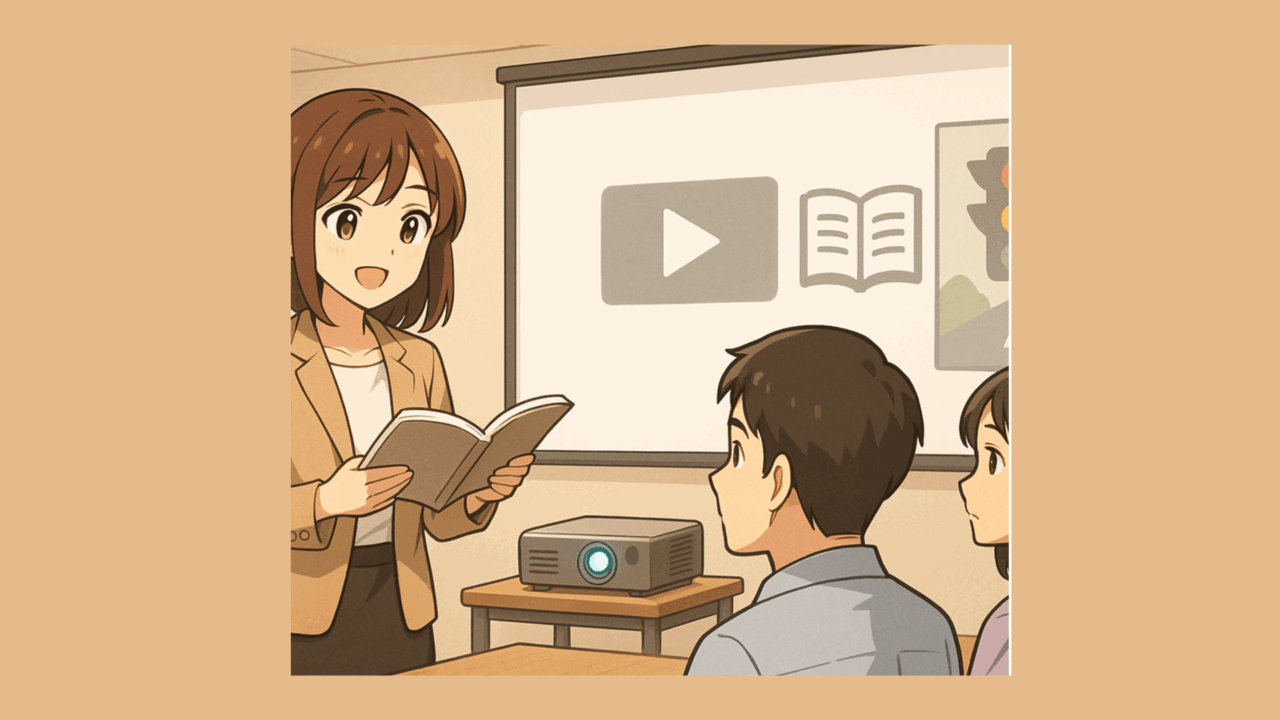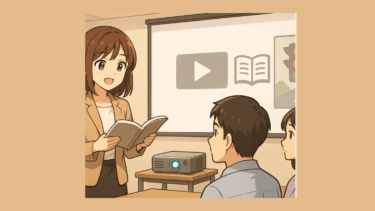どうも。
スマイルネットワークのコージリです。
飲酒運転を防ぐには「やらない」と意識するだけでは足りません。
人の行動を変えるには、心を揺さぶる体験が必要です。
私は前職の某大手企業で行われていた取り組みに触れ、朗読や映像、専門家講話が社員の心を大きく動かす力を持つことを実感しました。
これらは「規模の大きな企業だからこそ導入できた仕組み」と思われるかもしれません。
しかし、朗読会や映像教材、講話は中小企業でも工夫次第で十分に取り入れられます。 例えば朝礼の5分を使った朗読や、地域団体の講話依頼など、規模に応じた方法で再現できるのです。
👉 そこで今回は、朗読・映像・専門家講話を通じた社員教育の効果と、中小企業でも導入できる具体策を紹介します。
声に出す言葉が心を震わせる──朗読の力
私が在籍した企業の取り組みの中で、特に印象的だったのが「贖いの日々」という作文の朗読でした。
飲酒運転で事故を起こし、交通刑務所で罪を償う受刑者が書いた文章を朝礼で社員が当番で朗読するのです。
読む側は緊張しながら声に出し、聞く側は被害者や加害者の苦悩を想像して胸を打たれる。
事務所内が静まり返り、涙ぐむ社員も多くいました。
これは「飲酒運転は絶対に許されない」という強烈なメッセージとなり、日常の行動を律する原動力になったのです。
中小企業でも、朗読会はすぐに導入可能です。
例えば朝礼の数分を使って、社員が順番にテキストを読むだけで十分効果があります。
大切なのは定期的に繰り返すことです。
映像が記憶に刻む“二度としない”という誓い
人は文字だけでなく、映像から強い影響を受けます。
事故の悲惨さを描いた映像を上映したとき、社員の表情は一変しました。
自分ごととして受け止め、帰宅後に家族へ話す社員もいたほどです。
専門的な教材を必ずしも購入する必要はありません。
公的機関が配布している交通安全の映像や、YouTubeなどで公開されている社会的メッセージ動画も活用できます。
重要なのは「映像を見た後に短く感想を共有する時間」を設け、社員同士で学びを言語化することです。
リアルな体験談が社員の意識を一瞬で変える
もう一つ効果的だったのが、専門家による講話です。
交通安全の専門家や、実際に事故の加害者・被害者となった方の話は、社員の意識を一気に引き上げました。
講師を呼ぶのが難しい場合、オンライン講演や地域の交通安全協会を活用する方法があります。
自治体や警察署も企業向けの出張講話を行っていることが多く、費用を抑えて導入できるケースも少なくありません。
意識を変えるのは単発でなく“仕組み化”の継続
朗読、映像、専門家講話…。
これらは社員の心を動かし、日常の行動を変える力を持っています。
重要なのは「単発イベント」ではなく、仕組みとして継続すること。
大企業で成果を上げた教育手法は、中小企業でも十分に応用可能です!
ぜひ「朗読」「映像」「講話」を組み合わせ、飲酒運転ゼロ企業を目指す第一歩として導入してみてください。